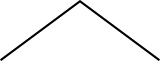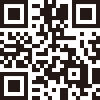つくる、つなぐ #4



第4回目のゲストは、陶芸家のクヴァジエ 彩さん。「手を入れすぎない」ことで表現される有機的な広がりのある作品が特徴。畳敷とヴィンテージの家具のミックスが心地よく調和するアトリエで、そのルーツと陶芸への思いを聞きました。
– 素敵なアトリエですね。どのように見つけられたんですか。
和室の部屋がほしくて、1年半くらい前に見つけたんです。畳の部屋で陶芸をするってちょっと面白いですよね。でも、それが不思議としっくりきて。
ここに来ると、まず換気をするんです。窓を開け、パロサントに火をつけて空気をリフレッシュ。それからは黙々と作業の時間ですね。自然光が差し込む中、手を動かしていくのが好きで。アイデアが浮かぶのは、飲み物を取りに席を立った瞬間だったりします。

– 陶芸の魅力はどんなところに感じていますか?
私は均質なものよりも、手のゆらぎが残るものに惹かれます。工場で作るのではなく、人の手でしかできない表情があるものが好き。だからこそ、制作するときも直感的に土の状態を見ながら形を作っていきます。たとえば、板の上にロープを丸く敷き、その上から粘土にやさしく触れながらお皿のふちを立ち上げたり。こうした手作業が、日常に馴染むおおらかな器につながるんだと思います。

– 作陶にはどんな土を使っているのですか?
京都の白い粘土を手でこねて、のべ棒で伸ばします。日本の土ってすごく面白いんです。練る時間や分量に数値的なレシピがあるわけではなく、感覚と、その日のコンディションを読みながら作っていきます。窯の温度はだいたい1200℃。その日の気分によって作りたいものを作っています。

– もともと陶芸を始めたきっかけは?
福島の郡山で自然に囲まれて育ち、高校卒業後にフランスへ渡りました。パリでは、マリーという陶芸家のアトリエに通っていました。そこでは、土や窯は自由に使えたけれど、あれこれ教えられるのではなく、わからないことがあれば自分から尋ねるスタイル。のびのびと学べる環境でしたね。日本に戻って東京でセラミックを作り始めたのは2019年からです。
感性や感覚については、祖母や母の影響が大きいと思います。イタリア生まれでパリ在住の祖母は、おしゃれで自由な人物。いつもパールのネックレスをつけていました。制作時に意識していたわけではないのですが、振り返ると、私の器の縁どりの丸い装飾とつながっている気がします。母は世界各地の器を集めていて、彼女が持っていた楽しげな絵付けの皿は、小さい頃から私の日常に溶け込んでいました。最近は、私自身もフリーハンドでお皿に絵を描くことに挑戦しています。
– たしかに、アヤさんの作品には、時間の経過を感じるような味わいもありますよね。
新品の既製品よりも、時間の経過が折り重なったものが好きなんです。アトリエにも自宅にも、ヴィンテージショップや骨董市で見つけた家具やオブジェが多いですね。パリにいた頃も、骨董品やヴィンテージの買い付けをしていました。だからなのか、私の作る器も、新しいのに、誰かの手によって長く使われてきたような雰囲気が出るのかもしれません。

– 素敵ですね。陶芸を続ける中で最も楽しいと感じるのはどんなときですか。
やっぱり窯を開けた瞬間ですね。出来上がったものと対面する、その一瞬がなにより嬉しいです。どんなふうに焼き上がっているのか、毎回少しずつ違う表情が生まれるので、いつもワクワクします。

1993年、福島県生まれ。高校卒業後に渡仏。パリで陶芸を学びながら、骨董品やヴィンテージの買い付け、現地コーディネーターとして働く。2019年に日本に帰国し、現在は東京を拠点にセラミックアーティストとして活動している。